最終更新日:Aug.19-1999
懐かしの「トリオ」の無線機カタログ
画像をクリックすると拡大されます(ブラウザの「戻る」を押してお戻り下さい)
★50MHz帯AM/FM機・TR-1100
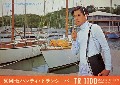 【1970年6月発行】
【1970年6月発行】
トリオ初、送受信にVFOを実装した50MHz帯ポータブル機。見かけ上はメインダイヤルは1つだが、実際は送受信で別のVFO(バリコンは1つ)を搭載しており、電波の発射の前にはキャリブレーションが必要だった。カタログの「トランジスタ17石、ダイオード8本を使い終段にもトランジスタを採用した本格的ソリッドステート。動作はきわめて安定です」というコピーが泣かせる。マイクはカセットテレコに付属してきたような筒型。付属のビニールレザーケースに入れて持ち歩ける。
★50MHz帯FM機・TR-5100
 【1970年8月発行?】
【1970年8月発行?】
アマチュア無線で最初にモービル運用のブームが起きたのは50MHz帯だった。なかでも人気だったのがトリオのTR-5100。50.8〜52.0MHzの範囲の最大12chのクリスタルを内蔵可能で、送信出力は10W。コレに1.5mある長いモービルホイップをしならせながら走るのが「粋」だった時代があった。その後技術の進歩と共にモービル運用ブームは144MHz帯へと移っていった。このカタログは4Pものだが、裏側はTR-5100を、表側は144MHz帯のTR-7100が表紙になった変わり種。すでに50MHz帯のモービルブームがピークを過ぎていたことがわかる。
★144MHz帯FM機・TR-7100
 【1970年8月発行?】
【1970年8月発行?】
そういうわけで、TR-5100カタログの表側にあったTR-7100のカタログの表紙がコレ。144〜146MHzのうちの12chのクリスタルを内蔵でき、送信出力は10W。価格は49,800円と、TR-5100よりも2,000円高かった。ちなみにカタログには「トリオ・カートランシーバーは5(ファイブ)メリットがあります」として、完全ソリッドステート、技術革新の成果IC&FETを採用、小型軽量設計、12のチャンネル数、万全な安全対策、の5つの特徴をあげている。
参考までに安全対策とは「車に安全基準があり、カートランシーバーに安全対策がないのは片手落ちです。TR-7100型、TR-5100型は、外観形状に丸みを持たせて角張ったところをなくし、突起部もできるだけ少なくし、ツマミには塩化ビニールをかぶせたものを使用するなど、安全に対して細心の配慮をくばっています」ということだった。
★144MHz帯FM機・TR-7200
 【1972年発行?】
【1972年発行?】
車載用無線機というと、今でもこの形を思い出してしまう、モービル機のベストセラーがこれ。約27年前の製品だが洗練されたデザインは少しも古さを感じさせない。鍵が取り付けられ、角度も変化できる車載アングル、底側に装備され少し前面に傾斜したスピーカ、1ボタンでコールchに移行できるQCSボタン、自己チェック機能つきONAIRランプなど、装備も斬新だった。また固定用のデジタル時計&タイマーとスピーカを装備した電源、PS-5(16,500円)も、あこがれの存在だった…。ちなみにこのカタログは6Pもので、表側はTR-7200を、裏側は430MHz帯のTR-8000が表紙になっている。
★430MHz帯FM機・TR-8000
 【1972年発行?】
【1972年発行?】
TR-7200カタログの背面に掲載されていた430MHz帯のTR-8000。パネルデザインはTR-7200とほぼ同じだが、パネルの地色がシルバーからグレーに変更されていた。価格はTR-7200が54,900円だったのに対し、こちらは89,800円と高価。周波数も431〜433MHz帯のうちの23chのクリスタルを入れられるというスペックだった。
リグが高く、運用者も少ないため、430MHz帯の運用者は現在の2400MHz帯よりも少なかったような印象がある。
★通信型受信機・9R59DS
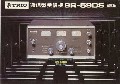 【1973年4月発行】
【1973年4月発行】
名機の呼び声高いHF通信型受信機キット・9R59Dの最後に出た“完成品バージョン”(29,800円)。カタログ裏面に「SWL・BCL用高性能受信機」とあるのが時代を感じさせる
★3.5〜28MHz帯SSB/CW/AM機・TS-511S
 【1973年3月発行】
【1973年3月発行】
TS-520シリーズ登場以前に一世を風靡したリグ。なんといっても終段に6LQ6を2本使用し、250W近いパワーが出たTS-511S(本体115,000円)が魅力だった。
★1.9〜28MHz帯SSB/CW/AM機・TS-900シリーズ
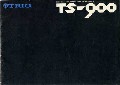 【1973年6月発行】
【1973年6月発行】
終段に4X150Aを使用したTS-900S(264,000円)、電源のPS-900S、外付けVFOのVFO-900Sを買うと348,000円という価格は、当時としては驚きだった。カタログもフルカラー16ページという凄さ。
★3.5〜28MHz帯SSB/CW機・TS-520
 【1974年2月発行】
【1974年2月発行】
八重洲無線のFT-101の好敵手として知られるHF帯トランシーバ。「AMモードがない」「1.9MHz帯に出られない」といったウィークポイントはあったが、デザインと性能の良さには定評があった。ALC切り替えに「DX」というポジションがあったのがローカル局の羨望の的だった。当初は10WタイプのTS-520X(99,800円)と100WタイプのTS-520D(114,800円)というラインアップだったが、その後1979年頃にマイナーチェンジを受け、1.9MHz帯を追加し、デジタルカウンター対応、スピーチプロセッサ搭載となったTS-520V(10W機=124,800円)と、100W機のTS-520S(139,800円)になった。
★50MHz帯AM/FM/CW機・TR-5200
 【1973年発行?】
【1973年発行?】
アイコムのIC-71と双璧をなす、50MHz帯固定機(69,900円)。オーディオ製品を連想させる黒いパネルと青の表示板がカッコ良かった。SSBは受信のみ可能だったが、52MHz以上の周波数はオプションのバンド水晶が必要だった。このカタログは同製品としては初期のもので、表紙には旧機種のTR-5000(50MHz帯5W固定機)の型番も併記されている。
★144MHz帯FM機・TR-7300
 【1974年2月発行】
【1974年2月発行】
「レジスター」という異名をとるデスクトップ機。カタログにも「通信機の常識を超えた新しいカタチ」と書かれているが、まさしくその通りだった。ボタン一発でどのチャンネルにもQSYできるリグは後にも先にもこの1台だけ?価格は99,800円だった。
★144MHz帯FM車載機・TR-7200G
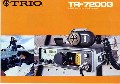 【1974年2月発行】
【1974年2月発行】
「2mのモービル機」というと、このカタチを連想するという人も多かった、144MHz帯FMモービル機の定番中の定番がTR-7200。八重洲無線がずっと「HFのヤエス(101のヤエス)」であった時代、トリオはVHF帯のモービル機の分野でもシェアを築いていった。これはTR-7200のマイナーチェンジ版で、22ch+VFO対応(実装8ch)だった(57,900円)。拡声器としても使用できるパワーアンプが便利だった。
★マイハンディ・TR-1200(50MHz帯AM/FM)/TR-2200G(144MHz帯FM)
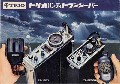 【1973年5月発行】
【1973年5月発行】
2台揃って“マイハンディ”というシリーズを構成していたが、TR-2200G(36,900円)は135W×58H×191Dmm、1.8kgという弁当箱サイズ。TR-1200(34,000円)に至っては185W×64H×235Dmm、3.0kgという大きなサイズ。別項でも触れたが、今では「どこが“ハンディ”じゃい!!」と文句を言いたくなるようなサイズだが、当時はこれが可搬機の標準的サイズだった。
なお、さるOMさんからTR-1200の単体カタログと、TR-2200の単体カタログの画像を頂戴したのでこちらも鑑賞していただきたい。
★ケンクラフトの50MHz帯SSB/CWキット固定機・QS-500
 【カタログに発行日記載なし】
【カタログに発行日記載なし】
「巣鴨のハムショップ」の話題でも触れた、トリオのキットブランド「ケンクラフト」の、50MHz帯真空管式トランシーバキット(59,800円)がこれ。各ユニットは完成していて、ユニット間の配線をしていけば完成する。…とはいうものの、組立には結構時間がかかった。
★144MHz帯FM機・TR-7500
 【1977年3月発行】
【1977年3月発行】
数回にわたるマイナーチェンジを受けたTR-7200シリーズは1977年に生産完了し、TR-7500に取って変わることになった。この機種はサイズが172W×60H×234Dmmと、TR-7200よりも一回り小さくなり、しかも145MHz台を20kHzセパレーションで50chフル装備(144MHz帯の50ch増設にはオプションのバンドクリスタルが必要)。周波数表示もデジタルになるなど、さまざまな点が新しくなった(余談だが、このリグに147MHz台のバンド水晶を入れる人が結構いたような気が…!?)。ちなみに価格は63,800円だった。
★50MHz帯SSB/CWポータブル機・TR-1300
 【1977年発行?】
【1977年発行?】
SSBが発射できる初の50MHz帯ポータブル機。144MHz帯のTR-2200GⅡと430MHz帯のTR-3200とコンビを組み、「ACTION HANDYトリオ」と呼ばれた。単3電池9本を使用し、実装済みのクリスタルとVXOの併用で50.075〜50.275MHzの送受信が可能だったが、バンドスキャンがなく、チャンネルごとにスキャンをかけていく必要があり、DXハントなどには少々やっかいだった…。着脱できる短縮コイル入りホイップアンテナ、別売の外付けVFOや10Wブースターなどのアイテムも懐かしい。このリグの登場で50MHz帯は一気にSSB化が進んだ感じがする。某入門誌はこのリグを使って「山手線電車モービル大実験」なる企画をやり、その携帯性の良さと通信距離の長さをアピールしたものだった…。
★50MHz帯SSB/CW/AM/FM機・TS-600
 【1977年11月発行】
【1977年11月発行】
50MHz帯のオールモード固定機。八重洲無線のFT-625DやアイコムのIC-551の好敵手だったが、FT-625Dは感度が良くて無理すれば50W近いパワーが出る、IC-551は(別売ユニットを入れなければ)価格が安く、周波数メモリーもできたということから、やや苦戦を強いられた感がある。しかしメカニカルなデザインは秀逸で、いまもこだわりを持ってこの機種を使っている人もいる。メインダイヤルは早送りと微調整が可能な二重ツマミになっているが、同時に両方をつかんで回すと10kHzステップで周波数がアップダウンできるという裏ワザがあった…。
★1.9〜28MHz帯SSB/CW/RTTY機・TS-820
 【1977年11月発行】
【1977年11月発行】
TS-520の上位機種として誕生したHF帯トランシーバ。周波数表示がデジタルとなったこと(820D、820Xはオプション)、RFタイプのスピーチプロセッサが装備されたこと、回転に応じて表示される数字が変化する新型のサブスケールダイヤル、IFシフト回路やCW時のオーディオ周波数特性変更回路などユニークな装備があった。その分価格は高く、100Wフル装備のTS-820Sで23万円、10W廉価版タイプのTS-820Xで178,000円した。
★短波帯受信機・R-820
 【1978年4月発行】
【1978年4月発行】
TS-820とデザインを共通にした高級短波帯受信機。といっても現在のようなゼネラルカバレッジではなく、受信できるのは1.8〜2.0MHz、3.5〜4.0MHz、5.9〜6.4MHz、7.0〜7.5MHz、9.4〜9.9MHz、11.5〜12.0MHz、14.0〜14.5MHz、15.0〜15.5MHz、17.7〜18.2MHz、21.0〜21.5MHz、28.0〜30.0MHzのSSB、CW、AM、RTTYに限られていた。TS-820が装備している受信機能は一通り網羅し、両者のトランシーブ操作も可能だったが、価格も21万円と高かった。
★1.9〜28MHz帯SSB/CW/AM機・TS-930
 【1982年3月発行】
【1982年3月発行】
社名はまだ「トリオ株式会社」だった、フロントパネルの銘板には輸出ブランドとして長年使用してきた「KENWOOD」のロゴが入った最初のリグ。100Wタイプの価格は299,800円。ファイナルまで含めてオール固体化。受信部を150kHz〜30MHzのゼネカバとし、本体内部にオートアンテナチューナーを搭載(チューナーをオプション扱いし3万円安くしたバージョンもあった)したのもこの製品が初めてだったと思う。
★3.5〜28MHz帯SSB/CW機・TS-130
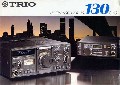 【1982年4月発行】
【1982年4月発行】
コンパクトで車載可能なHF機、TS-120をマイナーチェンジしたのがこの機種(100Wタイプは139,000円)。1979年の国際会議で追加割り当てが決まった新アマチュア無線バンド(10、18、24MHz帯)に対応したり、スピーチプロセッサの搭載、CWナローフィルタを搭載可能にするといった点が新しかった。またオプションでモービル用のコントローラ、DFC-230(43,000円)も接続できるようになった。
※制作に際し、貴重な資料をご提供いただきました各位にお礼申し上げます。
前のページへ戻る
トップページへ戻る
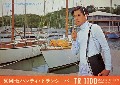 【1970年6月発行】
【1970年6月発行】 【1970年8月発行?】
【1970年8月発行?】 【1970年8月発行?】
【1970年8月発行?】 【1972年発行?】
【1972年発行?】 【1972年発行?】
【1972年発行?】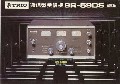 【1973年4月発行】
【1973年4月発行】 【1973年3月発行】
【1973年3月発行】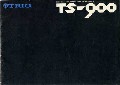 【1973年6月発行】
【1973年6月発行】 【1974年2月発行】
【1974年2月発行】 【1973年発行?】
【1973年発行?】 【1974年2月発行】
【1974年2月発行】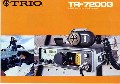 【1974年2月発行】
【1974年2月発行】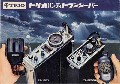 【1973年5月発行】
【1973年5月発行】 【カタログに発行日記載なし】
【カタログに発行日記載なし】 【1977年3月発行】
【1977年3月発行】 【1977年発行?】
【1977年発行?】 【1977年11月発行】
【1977年11月発行】 【1977年11月発行】
【1977年11月発行】 【1978年4月発行】
【1978年4月発行】 【1982年3月発行】
【1982年3月発行】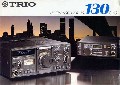 【1982年4月発行】
【1982年4月発行】